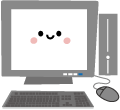自作パソコンの話を聞いて、少し憧れるのが「オーバークロック」と呼ばれる手法でパソコンの機能をアップさせることかもしれません。
パソコンは内部の部品や回路が処理のタイミングを合わせるため基準となる周波数を持っていますが、CPU はより高速な計算をさせるため、基準周波数を一定の倍率で引き上げた「動作周波数」を使っています。
「動作周波数」は「クロック周波数」とも呼ばれ、この「クロック」をメーカーが安定動作を保障する定格よりも上げて CPU の処理速度を上げよう、というのが「オーバークロック(over clock)」です。
「オーバークロック」するには基準の周波数を上げるか、引き上げる倍率を増やすかになりますが、マザーボードにその変更ができる機能があれば、それを BIOS や専用ソフトで調整することになります。
ただしマザーボードによっては「オーバークロック」できない設計になっているなど、どんなパソコンでもできるわけではありません。
そして CPU をはじめ、部品メーカーは定格動作周波数を越えた状態での動作保証はしていないため、自己責任で行なう必要があります。
もちろん動作する限界があるので注意して試すことになります。
部品の動作周波数が上がると、その分、電力消費が大きくなり、発熱も増え、温度が上がります。そのことで部品の寿命が短くなったり、故障することもあるため、冷却ファンなどの強化が欠かせません。
最近の CPU は高速処理が必要なときに温度的に余裕があれば自動で動作周波数を上げる機能を持ったものもあり、普通の使い方をするのであれば無理に「オーバークロック」する必要はありません。
とはいえ、「オーバークロック」は自作パソコンの醍醐味ともいえるので、やってみたい気持ちは十分に理解できます。
「なにしろパソコン」では記事内に Amazon や 楽天 が販売する商品へのリンクや画像を掲載することがあり、そのアフィリエイトリンクを経由して商品の購入があったときに販売元から広告収入を得る場合があります。
記事の情報は公開時あるいは更新時のもので、最新情報はリンク先など情報元の公式ページでご確認ください。