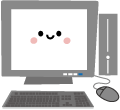「パケット(packet)」は英語で「小包」の意味がありますが、類義語の「パッケージ(package)」と比べると、より小分けされたイメージです。
ネットワーク上に大きなデータを一度に切れ目なく送信すると、その間、他のデータが流れにくくなり、また送信中に接続が切れたら、途中で情報が失われることになります。
そこでデータをあとで元に戻せる程度のサイズに分割して、小分けにして送る方法が考えられたわけです。
小分けしたデータそれぞれに、送り主と送信先のアドレス、さらに間違いなく元に戻すための情報(制御情報)を加えたものが「パケット」であり、「パケット」に小分けして情報を伝える方法が「パケット通信」です。
インターネットの情報交換には、この「パケット通信」が使われています。
「パケット」はイメージとして回転ずしに少し似ているかもしれません。
ネットワークが回転ベルトで、そこに流れるパケットはお皿、お皿の上に載っている寿司が情報という感じです。
回転ベルト上にお皿が並んでいても、板前さんは新しいお皿を隙間に割り込ませることができます。
お客さんはお皿が別々に流れてきても、順次、上に載っているネタを確認して自分の頼んだ寿司を取り上げることができます。
これなら複数の板前さんと複数のお客さんがいて、一度に複数の注文を受けても、ひとつの回転ベルトで効率よく届けることができます。
もちろんインターネット通信の場合、複数の接続ルートがあるので回転寿司ほど単純ではありませんが、情報を小分けにする利点はイメージできると思います。
「パケット通信」なら通信が混みあっていたり、通信速度が遅い場合でも送受信できる可能性が高くなります。
通信の混雑具合や速度は一定でないため、インターネット接続サービスでは「つないでいる時間」よりも「送受信した情報量」で通信料金を設定するのが一般的になっています。
さらに通信料が増えた現在では、インターネットに常時接続しても月に一定額を支払えばパケット量に関係なく、無制限で利用できる契約が主流になってきました。
携帯電話でもインターネット経由のサービスでは「パケット通信」となります。
年々、携帯電話による「パケット通信」は増え続けているため、ここでも定額でパケット使用量の制限がない契約が導入されています。
追記(2012/1/9)
スマートフォンの普及によりパケット量が激増しているため、定額制を維持するのは厳しく、使用量が制限される可能性もあります。上限などが決められると気軽に使えなくなるので定額制は維持してほしいです。
「なにしろパソコン」では記事内に Amazon や 楽天 が販売する商品へのリンクや画像を掲載することがあり、そのアフィリエイトリンクを経由して商品の購入があったときに販売元から広告収入を得る場合があります。
記事の情報は公開時あるいは更新時のもので、最新情報はリンク先など情報元の公式ページでご確認ください。